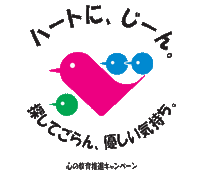学習・進路活動
総合的な探究の時間(1学年) 苫前町夕陽ヶ丘風力発電所見学
6月20日に1年生の総合的な探究の時間で苫前町夕陽ヶ丘発電所の見学に行って参りました。苫前町出身の生徒は小中学校の時に見学したようですが、それ以外の生徒にとっては風力発電所の風車にこれほど近くまで来て、タワーの内部を見学するのは初めてのようでした。
現地では苫前町役場建設課の高田和彦様から、風力発電所に関する説明がありました。「強い風」「広い土地」「旧国道や農道などの既存の道路」「羽幌炭鉱の遺産としての高圧電線」「地域住民の理解」という5つの条件がそろっていたため、苫前町は日本最初の大規模風力発電地帯となったというお話に強い印象を持ちました。
総合的な探究の時間(1学年) 羽幌ビオトープ公園生物調査
6月16日(月)、1年生の総合的な探究の時間で2校時から4校時まで、羽幌ビオトープ公園での生物調査に行って参りました。学年をAグループとBグループに分け、水生生物の調査と植物・昆虫の調査を羽幌シーバードフレンドリー推進協議会の方々の指導とサポートをいただき行いました。生徒たちはこのビオトープに来たことはあるとのことでしたが、胴長靴をはいて北海道池の中に立ち込むことは初めてとのことでした。池の中にはオタマジャクシ、ヌマエビ、ドジョウ、ヤゴなど想像以上に多種多様な生き物がいて、生徒たちも童心に返り楽しんでいました。デジタル化やバーチャル化が進む世の中ですが、やはり五感を駆使して自然を「体感」することの重要性を感じました。
総合的な探究の時間(1学年) 羽幌ビオトープ生物調査事前講演
6月10日㈫、1年生の総合的な探究の時間で北海道海鳥センター職員越宗菜保美さんをお招きし、6月16日㈪に実施予定の羽幌ビオトープ生物調査の事前講演をしていただきました。
羽幌ビオトープの生物調査によって生物多様性に関心を持ってほしいとのことでした。生物多様性とは、いろいろな生物がいろいろな環境で暮らしていることですが、環境問題の悪化をきっかけに誕生した言葉だそうです。生物多様性にもいくつかのカテゴリーがあり、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「種内の多様性」についてお話をいただきました。
講演の最後に、生物を見つけるトレーニングを行いました。15秒以内に野生生物の特徴をつかんだイラストを描くというもので、色や形、大きさがわかるように描くのがポイントだそうです。
講演終了後に質疑応答があり、生徒からは「危険生物に出会ったらどう対応するか。」「北海道池はどのように造られたのか。」という質問が出ました。
総合的な探究の時間(1学年) 羽幌町役場の地域振興施策

5月30日㈮、1年生の総合的な探究の時間で羽幌町役場地域振興課政策推進係主事の渡邊将平様をお招きし、町役場の立場で羽幌町の振興にどう取り組んでいるかお話をしていただきました。
まず最初に、高校生が目標を定めて勉強するのと同様に町も羽幌町総合振興計画という目標を策定しすべての事業を進めているということでした。現在は第7次振興計画を実行中で、農林水産業や観光振興の具体例をお話いただきました。また、健全な行財政運営および医療・介護・福祉の充実にも取り組んでいるとのことでした。一例として、羽幌町で赤ちゃんが生まれたとき、ご両親に焼尻産緬羊の手作り布団がプレゼントされるとのことです。町の魅力を発信し、移住者の拡大を図ることも目指しており、これを第三の人口と呼んでいるとのお話もありました。生徒は、行政という立場での非常に細やかで具体的な施策を知ることができました。
総合的な探求の時間(1学年) 地域振興講話


5月20日㈫、1年生の総合的な探究の時間で羽幌町地域おこし協力隊の行方和之様をお招きし、地域振興に関するお話を伺いました。
地域おこし協力隊は都会に住んでいる人が地方に移り住みやすくする制度であり、地域振興の要諦は地域の活力を引き出し、作り出すことによって住みやすい生活の場を作ること。そのためには今住んでいる町のことをよく知る必要があるとのお話をいただきました。
講話の最後に、高校生の立場から羽幌町がより住みやすい町になるための提案として、ファストフード店やゲームセンターをはじめ、若者が集い、買い物に便利なショッピングモール、バッティングセンター、リーズナブルな価格のカラオケ店、遊園地などを作って欲しいという意見が出ました。さらに、JRを復活させ、廃墟となった建物を撤去し、そこに先ほどのような施設を設置して欲しいという意見もありました。また5Gの回線を早く整備して欲しいという意見もありました。
本校の不審者対応および時間外の校内体制等についての周知文書です。
⑴ 令和6年度 学校評価の集計結果を公表いたします。
♢交通機関
通学バス
・豊岬-初山別-有明
-築別-羽幌高校(43分)
・古丹別-上平
-苫前-羽幌高校(28分)
・留萌駅前-鬼鹿三区
-苫前-羽幌高校(75分)
〒078-4194
北海道苫前郡羽幌町南町8番地
T E L 0164-62-1050
F A X 0164-62-1051
E-Mail
haboro-z0★hokkaido-c.ed.jp
(スパムメール対策のため★を@に置き換えてください)
このサイトに掲載されている画像及び文章の無断での転載・コピーについては固くお断りさせて頂きます。
北海道羽幌高等学校公式Instagram(https://www.instagram.com/haboro_highschool/)
北海道羽幌高等学校公式note(https://haboro-hs.note.jp/)
北海道教育委員会公式note(https://hokkaidopref-edu.note.jp/)